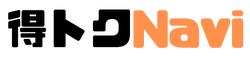価格:2640円(ポイント 80pt)
実質価格:2560円
ブランド:朝日新聞出版
評価:★★★★☆ (4.3 / 5)
📢 Amazonでの購入者の声を紹介します
【1】
コトラーのマーケティング論にはエビデンスがないと断じ、データからマーケティングのリアルを追求する。名指しで批判するのは品がないと思うが、定説に喧嘩を売るという姿勢が趣旨になっているので、これもマーケティングなのだろう。内容は、基本的にはSTPを机上の空論とし、知名度の高いブランドがロイヤリティも高い(というか本当はロイヤリティなんてほとんど存在しなくて、他のもののことを深く考えるのが面倒なのでリピートするだけ)ので、マスマーケティングしましょうという話。確かにデータはそれを示している。個人的には、インターネット以前のデータではこんなものだろうという感想。要するに、なぜ購入されているのか分からないからこういう結論しか出せないのでは。2024年現在、この話を全面的に信じてはいけないのではないかと思う。もっと細かくデータを見ることが可能なのだから、本書を踏まえつつ超えることは容易なのではないか。一方で、理屈が先行しすぎているマーケターに対して、目を覚まさせるには良いと感じた。少し冗長だが良書。データを軸に語る書籍は古典になりうるのかという疑問を抱きつつ星5つ。
【2】
本書に示されている内容は、すべての業界や商品に必ずしも当てはまるわけではない。しかし、すべてのマーケターが一つの視点として持っておくべき考え方であることは間違いない。本書が発売されてすでに7年以上が経過しているにもかかわらず、「顧客とのリレーション」や「ストーリー」といった言葉が、マーケティングの世界ではいまだに当然のように語られ続けている。しかし、顧客の視点に立って改めて考えてみてほしい。いくら日常的に利用しているブランドであっても、そのブランドとの「リレーション」を本当に求めているだろうか。「ストーリー」に関心を持っているだろうか。自分の身の回りを見渡してみても、そのようなブランドがいくつあるだろうか。残念ながら、私はマーケターとして20年の経験を有するが、一人の消費者として、そのようなブランドは数えるほどしかない。
【3】
大変勉強になります。ただ、名著にはたいだい「品」というものがありますが、この著者はコトラー批判ありきなので品位を落としているのがもったいないです。「差別化」より「独自性」とありますが、独自性は差別化の一種であり差別化の延長線上にあるものだと思います。なので、コトラーから学んだ発展形と表現した方が名著たる品が生まれると思います。いずれにしても読むべき一冊で、目から鱗です。
【4】
主な主張は、・ライトユーザーにアピールせよ・広く、様々なシーンで思い出してもらえる記憶構造を作ることが大事です。現在のマーケティング施策の主流は、STP(Segmentation, Targeting, Positioning)理論でブランドの立ち位置を決めた後、CRM(顧客管理)を使って、その限定したターゲットのロイヤルティを極限まで高め、高効率なマーケティング施策を展開し、ROIを高め、特定顧客からの高評価を獲得する… みたいなことが言われています。本の主張は、これって正しいの? その根拠は? 成功事例は? その施策で売上はどう変わるの? ということを確かめるというスタンス、要はこれまでのマーケティングの常識は間違ってるよ、ことです。極端な言い方ですが、マーケティングの担当者は過去の言い伝えに頼って、中世の医師たちと同じことをしている(悪い血を抜くといって、命の危険にさらしているだけ)とまで言っています。マーケティングに無駄な時間とお金を費やしている、特に、広告は無駄が多いと。で、本の内容は、ユーザーの特徴、ブランディング、広告、価格戦略、ロイヤルティプログラムについての説明があって、後半に、「これまでのマーケティング→これからのマーケティング」特に、重要な視点として、「メンタル・アベイラビリティ(ブランド想起の高さ)」「フィジカル・アベイラビリティ(購買機会の高さ)」の説明があり、今後やるべきことが最終章に書かれている構成です。マーケティング施策について、これってほんとに効果あんの? という疑問を持った方がいれば、早めに読んだほうがいいかもしれませんね。
【5】
新鮮な切り口でブランディングを語る一冊。まだ序盤ですが、"ダブルジョパディの法則"は、既存客向けのサービスに偏ることが、長期的なブランド成長にはあまり効果がないことを示しています。私の携わる業種では、ややもすると、顧客との、ある種の内輪ノリが歓迎されるところがあり、これは盲点かもしれないと、気づきを得ています。この手の書籍の中では込み入った内容で、真摯に書かれた一冊という印象を受けます。ひとまず、読み進めてみます。
【6】
同じことを一冊に渡って主張している。最初は一生懸命データから語っているが、だんだんデータは登場しなくなる。内容としてはそれはそうだよな〜という感想で良い内容だったと思います。
【7】
ダブルジョパディの法則が多用されている本。読み砕くのが少し大変。
【8】
真っ向からコトラーを否定している筆者。マーケティングに関わる上では、定量データを多く揃えており説得力はあるので新知識として抑えておきたいところです。ただ、コトラーが当てはまるケースとバイロンシャープが当てはまるケースと、両方とも正しいと思っているので、この本が絶対正とは思わないほうが良いという認識です
【9】
気難しい感じの執筆者
【10】
メインの感想は、重要なことが難しく書かれている本。学者特有の問題なのか、訳書の問題なのか、書き方の癖が強い。さらっと読める感じではなく、一文一文追いかけて初めて意味が分かる。なので読むのにとても時間がかかった。書かれていることはどれも重要なことで、まさに誰も知らない法則なのだが、ネットやスマホ隆盛の今でも同じことが言えるのか疑問。(続編があるらしいので、そちらに書かれていたりするのか?)少し攻撃的なところがある(外国では当たり前?)が、有名な理論でも実は、科学的な根拠があるわけではない事には驚いた。この手の本によくある事だが、問題点の指摘の比重が高く、解決提案が少ない。大学の教科書としては星5、社会人の実用書としては3、間をとって星4とした。
※この記事は 2025年6月27日 時点の情報です