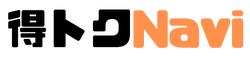評価:★★★★☆ (4.4 / 5)
📢 Amazonでの購入者の声を紹介します
【1】
エフェクチュエーションに関してとてもわかりやすく紹介したもの。本家のサラスバシーの本は詳しすぎて読みにくいが、本書は今の日本の企業を例にわかりやすく説明している。エフェクチュエーションの精神は、ビジネスの世界だけではなく日常的にも役に立つので、起業とは関係なくても読んでみてほしい。エフェクチュエーションを学びたいときにぜひ紹介したい本。
【2】
アクションし続けるための様々なメソッドが紹介されており参考になるが、自分が何に関心があるのかを大切にするのが一番大切であるように感じた
【3】
現代ビジネスでは、しばしば「先を読む力」や「データ分析」が強調されます。確かに予測可能な分野では、それらが大いに役立つでしょう。しかし、本書は「予測できない領域こそ面白い」という視点を提示し、そこにこそ新しい価値創造が潜んでいると説きます。キーワードとなるのが「エフェクチュエーション」。これは、高い不確実性の下で新事業を次々と成功させる熟達した起業家が、無意識的に使っている意思決定パターンを5つの原則にまとめたものだそうです。一つひとつの原則を見ていくと、「いま持っているリソースを起点に小さく着手する」「失敗しても大丈夫な範囲だけ投資してみる」「予期せぬハプニングを逆手にとって活かす」「自分のアイデアや思いに賛同してくれそうな人をどんどん巻き込む」「結果がどうなるかは分からなくても、自分のコントロール可能性に集中する」といった内容。この考え方は、ビジネスだけでなく、新しい趣味やキャリアづくりにも有用だと感じます。具体的な事例として、まったく新しいサービスを立ち上げた事例や、スペインの「パエリア」から「多目的仮設空間建築」へ展開してしまう面白いエピソードなどが登場します。特に印象的なのは、最初は「こんなことになろうとは想定していなかった」という言葉の数々。要するに、当事者ですら計画していなかったことが、偶然の出会いと行動の連鎖で新しいビジネスになっていく。その姿こそが「エフェクチュエーション」だというのです。従来の「コーゼーション(因果論)」――目標→分析→計画→実行というフレームワークに囚われていると、確かに最初から市場調査やビジネスプランを詳細に作り込み、リスクを避けようとしすぎるあまり、実際には身動きが取れなくなるケースがあります。しかし本書は、「失敗のリスクより、行動しないリスクのほうが大きい」とも教えてくれます。もし失敗しても“許容可能な損失”に収めておけば再挑戦は可能。一方、何もせずに機会を逃してしまうと、今ある資源すら活かせないまま終わってしまう。また、他者をどう巻き込むかという「クレイジーキルト」の部分は、多くの人にとって興味深いと思います。自分とは全然違うリソースやビジョンを持ったパートナーを巻き込むことで、新しいアイデアや市場が生まれる。実際に、多くのスタートアップが成功を加速させるのは、予想もしていなかったアライアンスや出資者の参画が得られたときです。そういう偶発性を取りこめるかどうかは、起業家側の「売り込み」よりも「問いかけ(asking)」というコミュニケーションのアプローチにかかっている、という指摘も納得できます。本書を通じて学べるのは、「ゴールが決まらなくても、むしろそれが普通」という割り切りや、「不確実性をあえて取り込む」という姿勢の大切さです。固定観念から解放され、「そうか、始めてみてもいいんだな」と気づく読者は多いはず。実践例や理論両面のバランスがよいので、起業初心者はもちろん、既存のビジネス理論を学んだ人にも新鮮に映るでしょう。何より、読後には妙な勇気が湧き、「まずやってみよう」という気持ちにさせてくれるのが、この本の最大の魅力です。
【4】
著者も書かれているように、エフェクチュエーションという言葉を知らずにその中身を実践している人は多々いると思います。エフェクチュエーションという言葉自体もそうですが、手中の鳥とか、レモネードとか、クレイジーキルトとかの原則のネーミングも、その語源に馴染みのない日本人には全くもって意味不明です。大した目新しさのない海外のコンセプトをあえてカタカナ語で日本で浸透させる意味を個人的にはあまり感じませんでした。
【5】
新しい概念を、平易な言葉でわかりやすく述べています。コスパも高い良書だと思います。
【6】
新規事業に向かう中でいろいろ悩んでいましたが、エフェクチュエーションという考え方がものすごくスッと入ってきました!事例もまるで物語を読むようにイメージが湧き、しっかり腹落ち出来ました。
【7】
単なる自己啓発系ビジネス本ではなく、根拠となる文献が示されているので、それなりに信頼度があがりました
【8】
サラス・サラスバシー教授の提唱した5原則について学ぶだけなら、本書を読まなくてもネット上に転がってるビジネス系の記事を読めば足りる。ただ、日本企業の実例、実践者(中村氏)ご自身の事例解説にページ多くが割かれている点で、本書は日本人の読者にとって良質な入門書となっている。マイクロ企業の経営者である僕にとっては、一歩を踏み出す勇気をもらえるコーチングを受けているような気のする本だった。中村氏による巻末の教育分野への提言を読んでいて、アマルティア・セン(ノーベル経済学賞受賞者)のケイパビリティ・アプローチとエフェクチュエーション原則の親和性を感じたが、2人の学者がどちらもインド人である点が興味深い。
※この記事は 2025年7月4日 時点の情報です