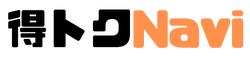評価:★★★★☆ (4.3 / 5)
📢 Amazonでの購入者の声を紹介します
【1】
大変おもしろく読みました。最新の状況を記述・解説した本は、これしかないので
【2】
人間の歴史の中で効率化が必ずしもすべての人に幸福をもたらすものではないことを理解できた。
【3】
テクノロジー万能ともいえる現代において、それを誰のために、どう使うかが、多くの人を幸福にするには重要!、というこれまで見落とされていたポイントを教えてくれた。AIの脅威が指摘される中で、対処方法の一つを知ることが出来、有用な一冊だと思います。
【4】
内容は面白いと思う、多分。多分というのは、翻訳が酷くて理解を妨げられたと思うから。早川書房という翻訳物を多数扱う出版社がこのレベルの翻訳を許してよいのだろうか。さらに章によって読みやすさが異なるので、2人の翻訳者のうちの1人が特に酷いのだと思う。並行して読んでいた「創始者たち」という本の翻訳が素晴らしく、翻訳者によってここまで違うのかと思わざるを得なかった。
【5】
前作からさらに技術革新と不平等という切り口で考察を深く進めている。非常に興味深かった。
【6】
過去1000年の新発明の事例は、一般人にその利益をもたらして来なかったが、第二次世界大戦後の数十年間、米国を始めとする工業国は、経済成長と労働環境の改善など、労働者にも利益をもたらして来た。その理由は、再分配制度と社会保障制度の大幅な拡大と政府規制の実施にあった。しかし、1980年以降は生産性の向上に比して賃金の成長は滞った。経営者の多くはオートメーション化による人件費削減を目指し、自動化による省力化は労働者の交渉力を弱くするという(労働者にとっての)悪循環が起こった。加えて労働組合の弱体化、アウトソーシングの流行などによってもそれらが加速されていった。そしてAIやロボットの活用が本格化する中、足元の技術革新は労働者の利益と相入れることができるかどうか、そうする為の条件とは何か、人類にとっての歴史的な転換点となり得る。
※この記事は 2025年7月4日 時点の情報です