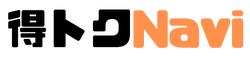評価:★★★★☆ (4.2 / 5)
📢 Amazonでの購入者の声を紹介します
【1】
本書は、「推し」の魅力やすばらしさを自分の言葉で語ることを目標にしていますが、それだけに留まらず、ビジネス文書、プレゼンテーション資料全般に通じる、普遍的な書く技術・方法論がまとめられています。本書を読むことで分かるのは、あくまで「正しいトレーニングのしかた」なので、要点を確りとおさえた上で、反復練習をすることが本当に重要なことなのでしょう。完璧な文章を書いたつもりでも、他者の添削や校正でダメ出しをされたりと、書くことの失敗から学ぶことも多い気がします。小学校の作文の授業でよくある、「ありのままに書いてみましょう」を、著者が否定的な捉え方をしているのことにも共感します。欧米のライティングの授業のような、実戦的な教え方の方が、作文の授業にはなじむ気がします。
【2】
「自分は何が好きなのか?」とずっとイラストの創作活動で悩んでいました。そんな時にこの1冊に出会い自分の好きなジャンルの傾向を分析し言葉にできるようになる糸口となって大変助けられました!特に前半3章の言語化する大切さ、「やばい」を分析する方法、相手に伝えるための心構えなどが機械的に細分化されています。また、全体的に優しい語り口でハードル低く書かれているので、0から言語化するためには大変気軽に試せると思います。一方、前半が良かった分、4,5章の実践編は前半の繰り返し気味に感じたので、6章のように実例の解説、表現の引き出しの増やし方などさらなる1歩に踏み出せる内容やもっと知りたかったです。全体を通して文章書きでなくても入門編として役立った本なので続きもあれば読みたいです!
【3】
大好きな推しの話をする人ってキラキラしている。まさに三宅さん。しかも、大丈夫だよ、あなたも言語化してみようよって招いてくれてる。ああ私も書いてみたいって、湧き上がる心。やばいしか出てこない私、チャレンジしてみます!
【4】
ついつい、ヤバい、すごい、で片付けてしまう最近。お仕事で初対面の方や価値観の違う方と話す機会が増えて、たまたまこの本を見かけて購入。肩肘はらずに自分の体験や感情を交えて表現することの大切さを知りました。
【5】
・本書は、文芸評論家で、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」などの著作を多数出版する著者が、現代において必須スキルである「自分の言葉をつくる」技術について伝えた1冊。・自分の「好き」を言語化するうえで、一番重要なことは、「他人の感想を見ないこと」である。・逆に言うと、「好き」を言語化するうえ一番NGなことは、他人の感想を自分の言語化の前に見えしまうことなのだ。・自分がまだもやもやした「好き」しか抱えていないとき、ほかの人がはっきりとした強い言葉を使っていると、私たちはなぜか強い言葉に寄っていくようにできている。・自分だけの言葉を手放さないようにするための第一歩として、自分の「好き」を言語化する前に他人の言語化を見ることは、やめること。・具体的に言うと、SNSやインターネットで自分の推しについての感想を見るのは、自分の感想を書き終わってから!!」。・SNSで他人の感想を読む前にひと呼吸おいて、まずは自分の感想をメモすること。すごく重要なコツなので、ぜひ実践することを著者はすすめている。※「自分の言葉をつくるための3つのプロセス」についても述べられているが、詳細は本書をお読みください。・言語化とは、「いかに細分化できるかどうか」である。・たとえば、あなたが好きなアイドルのライブについて語りたいとしたとき、「ライブ、すごくよかった。あのよさを言語化したい。」と思ったときにまずやるべきは、「自分は」「どこが」よかったのかを具体的に思い出すこと。・「好きだった」「よかった」「感動した」ところを挙げてもいいし、反対に「嫌だった」「違和感を覚えた」「好きじゃなかった」ところを挙げてもいい。・具体的に書くだけでなく、自分に嘘をつかずに挙げること。無理して「よかった点だけ」挙げるのではなく、「違和感を覚えた点」も含めて挙げることで、より自分の感覚を深く言語化することができる。・嘘をつかず、楽しくできる範囲で、具体的に感動した点を挙げるのがポイントだ。※フィクション(小説・映画など)、イベント(音楽ライブなど)、人(アイドル・俳優など)の具体例の挙げ方について述べられているが、詳細は本書をお読みください。・本書は、「推しを語ることは、自分の人生を語ること」「推しを語る前の準備」「推しの素晴らしさをしゃべる」「推しの素晴らしさをSNSで発信する」「推しの素晴らしさを文章に書く」「推しの素晴らしさを書いた例文を読む」という章で構成されており、◇感想は「〇〇〇〇の感情」が一番大切◇〇〇の言語化は、案外難しい◇一番重要で、一番難しい「〇〇〇〇」◇「〇〇〇」の真似は、上達への近道といった推しについて自分の言葉で発信するための技術が紹介された内容となっている。また、巻末には、「オタク口調を脱したい」「他人の発信にイラッとしてしまう」といった推しの素晴らしさを語るためのQ&Aが収録されている。あなたの「推し」をたくさんの人たちに届ける技術を知りたい方は、ご一読ください。
【6】
本文は「推し」を勧める文を書く際の懸念事項について書かれている感じですが、もっと敷衍して、こういったレビューなどにも使えるイメージを得た感覚でした。文章を取り敢えず吐き出してしまって、あとで推敲して並べ替える手順であったり、非常に実践的に書かれているのが良かったです。一番印象に残ったのが、「誰に向けて書くのか」を意識して書くと良い、という部分で、これが冒頭のレビューにも使えるかも知れない、との所感に繋がりました。後半部分が少し冗長な感覚を受けたので、レビューは星4評価にします。ですが十分に実用的な本だったことは付け加えておきます。
【7】
とてもよかった!
【8】
この本を読んで良い気づきがありました。自分もレビューで他人の意見をつい見てしまい、それに流されることがありました。先入観や自分が受け取った感性を塗りつぶされて、本当の自分とは?となる感覚が多かったです。自分と他人の意見を切り分けて,まず自分がどう感じたか?を言語化することで、本当の自分と向き合っていきたいです。
※この記事は 2025年7月2日 時点の情報です