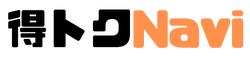評価:★★★★☆ (4.4 / 5)
📢 Amazonでの購入者の声を紹介します
【1】
「仕事ができる人って、そもそも何が違うんだろう?」とずっと思っていましたが、本書を読むとそれが意外なほど“当たり前”なことの積み重ねだとわかりました。実行力・決断力・コミュニケーション力などを章ごとに整理してくれるので、自分はどこが弱いか、どう補えばいいかが明確になります。たとえば、コミュニケーション力の章で「話のわかりやすい人」とはどういう人かを8つの視点からまとめている部分が大変参考になりました。結論から話す、相手に合わせて専門用語を調整する、話が脱線しそうなら一度完結させてから別の話題へ移る──こう聞くと単純ですが、「たしかに意識していなかった」と思わされる要素ばかり。それを“自然にできている人”が職場にはいるんですよね。また、ほかの読者レビューでも「なるほど」と思ったのは、「辞めどき」の話です。会社や上司に不満があっても、ただ耐えるのではなく、自分の人生時間を無駄にしないために“辞めるべきタイミング”を見極める重要性が語られています。とはいえ、すぐ辞めればいいというわけでもない。そこでは会社のルールを知り、自分が思う以上に社内営業を意識する、評価基準を理解するなど、きちんとした手順を踏むことが大切だと学べました。加えて、一見すると厳しいテーマも「やさしい語り口」で提示されるのが本書の魅力だと思います。要点を章の冒頭や見出しで示し、豊富な事例やケーススタディで深掘りする形式なので、ビジネス書になじみが薄い方でも読みやすいです。実際、他の方のレビューでも「社内の研修テキストとして配りたい」という声がありました。個人的には、「最初にアイデアを出す人こそ大事」「目標は達成し続けるより、時には失敗があったほうが結果的に伸びる」などの指摘も興味深かったです。仕事の壁を前にするときに、この本を開くと自分なりの判断軸を持てるようになると思います。
【2】
勉強になりました。上司の立場や仕事の本質を考えられるようになったと思います。上部だけいい上司を取り繕う人より、ここに書かれてる人が尊敬されると思います!
【3】
様々なビジネスケースに対して、合点、異なる視点、自分がやりがちな良くない考え方などが記されており、自分のビジネスマンとしての現在地を気付かされました。自分に課題のある項は何度も読み返すことで得るものは多くあります。
【4】
これまで仕事してきた中でけっこう意識してきたことが多く書かれていますうっかり忘れてることもあってもう一度意識し直そうと思います。「やってみたいは迷信やってみたは科学」考えるだけでなく実践するか。実際に行動しないと何も始まらないんですよね。やって失敗することも勉強なんですよね。ちゃんとPDCAを回すことを意識し直そうと思います。「大人は可能性と引き換えに目標を決める」新採の頃は自己効力感高めで過ごせるんです。ただ経験を積んで自分の道がなんとなく見えてくるとその道を突き進んだ方が良いんですよね。人生の時間は有限です。だから勇気を持って目標を決める必要があります。「仕事をするときは常に最初に案を出す」これはしてなかったです。ただ上司からしたら議論の先鞭をつけてくれるのは本当に助かります。話が動かないのが一番困るので。一番最初に案を出せるようになるように頑張る人はちゃんと評価しないといけないと思います。「相手の趣味好きなものを必ず聞いて教えてもらったらとりあえず試す」ググってみるくらいはするんですけどね。実際にやってみたりみてみたりするところまではやってないかなあと。たしかにそこまでやってもらったら一気に親しくなるなあと思います。「相手の意見を合理的だと考え自分の意見に自ら反論してみる」異なる考えを何の意味もないと切り捨てると対立しか生まないということです。まずは受け入れてみて何を言いたいのか考えてみる。それから自分の意見に足りないところがないか考えてみる。なかなか難しいですがやっていこうと思います。読んでみて思い出すことも多くてまだまだ頑張らなあかんなあと思います。
【5】
仕事を行う上で自分のためになる本でした。この本の内容を実践できるようにしていきたいです
【6】
業種によらない汎用的な、「中堅以上の仕事を進め方」のバイブルとなる本だと思います。(もちろん、若手の方が読んでも為になる本です。若手で読んでこれを実践すれば、昇進が早くなるでしょうね。)社内外の人との関わりの中で仕事を進める上で重要なことが、分かり易くまとめられています。下記のような方に特にオススメです。・自分の仕事の進め方をより良くしたい人・現状、自分の仕事の進め方が上手く行っていないと思っている人・自分の能力に対して評価が低いと思っている人汎用的に書かれているので、人によって為になる箇所は違うかと思います。ある程度業務経験があれば自分の弱点やスタイルを把握しているかと思います。それを踏まえて、この本の内容と自分を照らし合わせることで、自分に足りない所、改善点が見出だせるので、そこを改善していけば自分の仕事の進め方を効果的に良くしていけそうです。この作者の別の本はあまり良くなかったですが、この本は読んでとても為になりました。
【7】
### 努力はなぜする必要があるのか?人生は不安なものだから努力をするこの不安というのがポイント不安を解消するには何かに没頭するのが楽(余計なことを考えなくて済むから)この不安はどこから来るかというと、暇や無為経由で襲ってくる努力する人はこの暇や無為に耐えられない人が多い。一方で、努力しない人は、努力を報酬を得るための対価と認識していることが多い。だから努力が報われるというフレーズに対してネガティブな印象を抱いてしまう(努力しても報われないことがあると主張する)努力と報酬は切り分けて考えよう。不安を和らげるために努力をするというマインドセットが大事。### 意見がぶつかる時に「敵」ではなく「合理的な人」と認識することで対話の可能性を模索する意見が衝突した際に、敵とみなしてしまうと議論が平行線になってしまい収束しない。だから、「合理的な考えを持っている人」と認識を改めよう。なぜ、合理的かというと、自分の意見に対して反論してみると分かりやすい。そこには敵という観点ではなく、合理的に意見を述べてそれが反対意見として表面化していることに気づけるはず。そう解釈すると、衝突ではなく対話の余地が生まれていることにも気づけるはず。### スキル向上の秘訣巷にはスキル向上のための「効率化」を謳った書籍で溢れているが、本質的には時間を使って投資するしかない。効率の良い方法はあるかもしれないが、レベルアップするための経験時間が3年から1年になることはない。毎日1時間投資すれば1年で365時間。10年で4000時間ほど投資できる計算になる。4000時間に達したら追いつくのは至難の業。### 目標設定会社における目標設定の意味を再定義しよう。本質的には自分が失敗を避けずにチャレンジを続けたかどうか?を盛り込んでいるかが重要。成果を出せるかどうかは確率の問題であり、短期的に成果を出せるものもあれ難しいものもある。長期的に見てチャレンジを続けることが、結果として成功の期待値は高くなるという考え方。ありがちな、目先のゴールが見える目標設定はNG。
【8】
自分の仕事や生活を振り返って、大切なのは、行動する事 を再確認しました。
※この記事は 2025年7月2日 時点の情報です