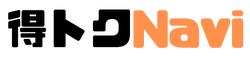評価:★★★★☆ (4.4 / 5)
📢 Amazonでの購入者の声を紹介します
【1】
面白かった。話し方の戦略ということで、話すときの言葉の選び方の本と思って買ったが、必ずしもそうではなかった。特に第1章が面白かった。「戦略の基本」とあるが、そこで書かれている3つの原則は、どれも「話す前」のこと。『頭がいい人が話す前に考えていること』と同じで、「話す前」の重要さについて説いている。「話す前」の重要さは、たまたまそれがクローズアップされていなかったものがクローズアップされるようになったのか。それとも、なにか時代の変化などの環境変化があって、より重要さが増しているのか。俯瞰すると、ここらを考えさせられ、学びになった。
【2】
YouTubeがこの一冊とのきっかけ。仕事上の立場が変わり『話し方』を意識する機会が増えました。そんな矢先にこの一冊に出会えことを嬉しく思います。
【3】
話し方の、プロの方も、毎回努力して、プレゼンテーションをしていることが、わかって目が覚める思いでした。非常に、良い本です。
【4】
興味がある方には響く良い書籍です!
【5】
あまり感銘を覚える本の内容出なくて、途中から読んでません
【6】
5000人以上のお客様のスピーチ向上支援実績を通して、再現性のある、体系だった方法論を解説してくれている、ビジネスパーソンなら一度は目を通して踏まえておきたい、必携の一冊です。言葉に加え、非言語表現も踏まえ、しかも才能がなくてもメソッドを知ることで誰でも身に着けることができるコミュニケーションの準備、今日から実践しようと思いました!
【7】
相手は聞きたいところしか覚えてくれない。だからこそ、話す側にはしっかりとした「戦略」が必要だと痛感させられる一冊でした。本書が教えてくれるのは、“話し方”とは単に「言葉選び」だけでなく、「声の出し方」や「身体表現」を含めた総合的なアプローチであるということ。これらを正しく使いこなすことで、相手の心に響くコミュニケーションを実践できるようになるのだと実感しました。まず本書で提示されるのが「3つの原則」です。一つめは「話す目的を明確にすること」。なぜ話すのかがはっきりしないままでは、つい余分な情報を盛り込みがちになり、結論がぼやけてしまいます。二つめは「対象者の分析」。相手が専門用語を理解できるか、そもそも話題に興味を持っているのかなど、前提を考慮するだけで不要な説明を省き、伝えたいポイントを的確に届けられます。三つめは「話し言葉の特性」。書き言葉とは違い、声は一度発したら消えてしまうものだからこそ、一文を短く区切ったり要点を繰り返したりして、耳で聞き取りやすく工夫する必要があるのです。続いて、本書は「言葉」の戦略を深掘りします。最初にコアメッセージを短くまとめ、次にそれを「ストーリー」と「ファクト」で支えるという流れです。ストーリーは自分の体験談や弱みを交え、“共感”を生み出す部分。ファクトは数字や社会背景など客観的な裏づけを与える部分です。これらを組み合わせることで、一方的な感情論でもなく、ただのデータの羅列でもない、人を動かす“説得力のある話”が完成します。さらに「レトリック」の章では、会話文を挿入したり印象的な引用を用いたりする具体的なテクニックも紹介され、“話の厚み”を持たせるためのヒントが満載でした。後半では、「声や動作」についてより実践的なトレーニング方法を提示しています。たとえば腹式呼吸を使った発声や、句点で2秒空ける“沈黙”のコントロール、フィールドを3〜6に分けて動き回る立ち位置の工夫など、映像で自分を客観視することで実感しやすい方法が多く、すぐにでも試したくなる内容です。中でも「フィラー(えー、あのー)をなくすには、思い切って“沈黙”を活用する」という考え方は目からウロコでした。録音や録画で自分を見返すと、意外なほどフィラーの多さに気づき、その上で沈黙を恐れずに活かすことがいかに大切かを学べます。本書の魅力は、“コミュニケーション下手だから仕方ない”と諦めていた私のような人にこそ、具体的な学び方を授けてくれる点。また、すでに自信がある人にとっても、自己流の話し方を客観的に見直すフレームワークとして役立ちます。結局のところ、「話が上手い人」と「そうでない人」の違いは、準備やスキルの意識をどれだけ持ち、どれだけ活かせるかにかかっている。本書は誰でも再現可能な方法を網羅しており、ビジネスから日常会話まで幅広く応用できる“普遍的なコミュニケーション論”だと感じました。
【8】
素晴らしい本です。伝える事の手法と伝える事が重要なんだと教わりました。今日から実践します^_^
※この記事は 2025年7月4日 時点の情報です